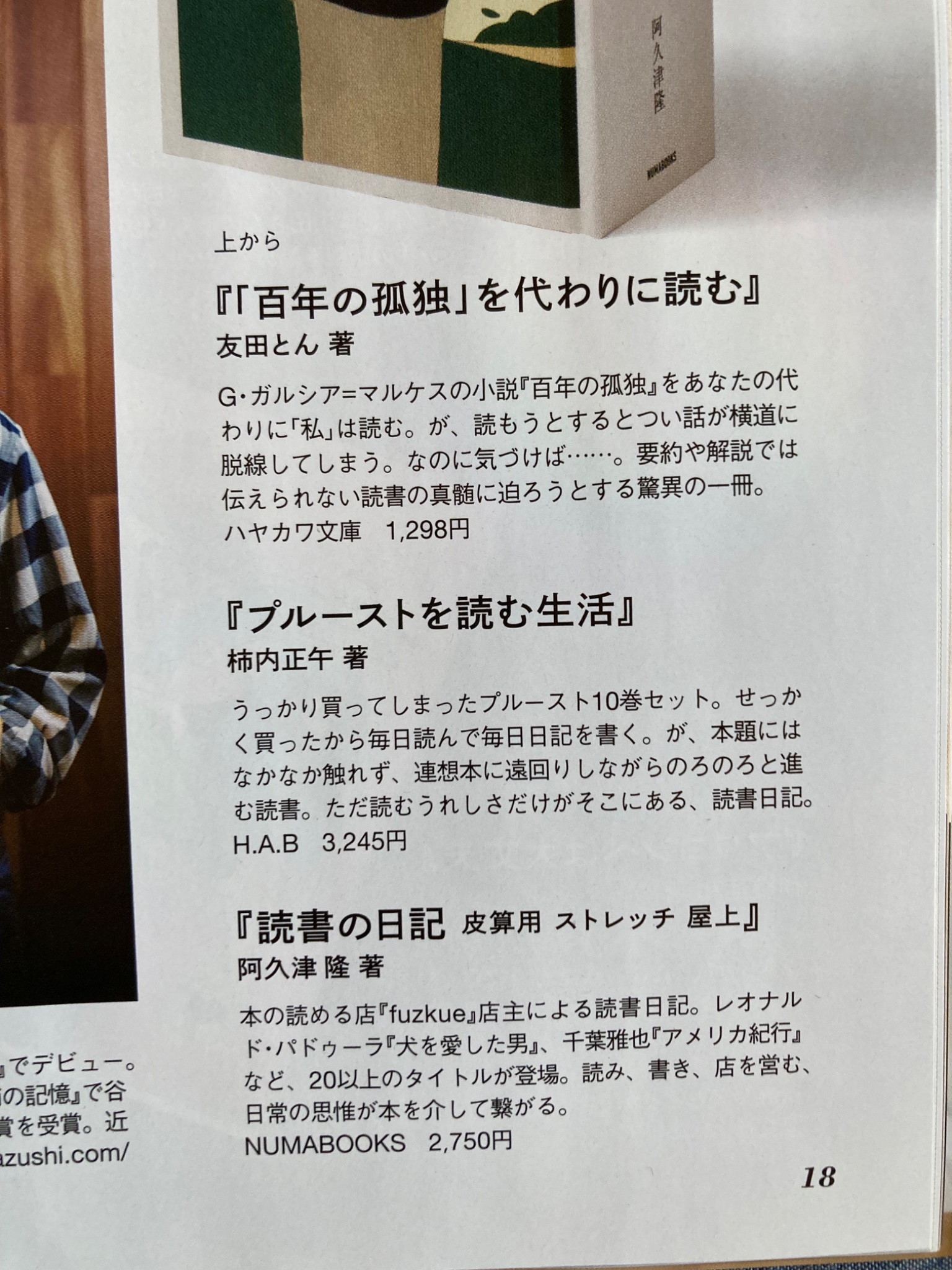少し変わった読書本を紹介しようと思う。
読書の習慣は、社会人になった時とか、人生で何度か危機があるが、その時に変わった読み方をする人の話を聞いてみたらどうか?
ただの読書家はつまらない。そういう人は型通りにしか本を読まない。そうでなく、一冊を最初から最後まで通読するのでなく、読み散らかす。本は通読しないと話題にしてはいけないとか、まして本を採点するとか、こういう考え方は学校で仕込まれた、読書感想文と作品要約の癖から抜けてない。
本を読むということは、社会に生きる個人が、自分ひとりの小さな空間を作って、それを維持することだ。読書に対する堅苦しい思い込みは捨て去って、好きなスタイルで読む。そうすれば、読書はきっと本当の意味で、人生の伴侶になると思う。
まず、『『百年の孤独』を代わりに読む』。
著者の友田とんさんはガルシア=マルケスの『百年の孤独』が好きすぎて、一人でも多くの人に読んでもらいたいという思いから、「代わり読む」という変な方法を考えついた。もちろんこれは朗読の本ではないーーそもそも本は朗読しない。
少し確認しておくと、本を読む人なら名前を知らない人はいないだろう『百年の孤独』が、ついに文庫本になったのが去年の六月で、出版界ではけっこうな事件で、文庫はベストセラーになったが、この本はそのずっと前、二〇一八年に著者の友田さん自身が自主制作したものだった。
だからごく一部の人以外には知られずに消えていく運命にあったんだろうが、文庫化されることは永久にないと言われていた『百年の孤独』のまさかの文庫化の決定が話題となったおかげで、この『〜代わりに読む』も早川書房から文庫として出版されることになった。一見ただのラッキーだが、その後、増刷を重ねているから、まんざら運だけでもない。
誰かが誰かの代わりに本を読むなんてできるわけがないが、「代わりに読む」という発想がともかく面白い。そして、読んでいくと、案外できてるような気がしてくる。友田さんは、『百年の孤独』を一章ずつ読みながら、四方八方に連想を広げる。落語の『粗忽長屋』、映画『バック・トゥー・ザ・フューチャー』『スタンド・バイ・ミー』、植木等の無責任シリーズ、テレビの『新婚さんいらっしゃい』などなど……などなど……
友田さんの連想の自由さは小説を読む気楽さ楽しさを教えてくれる。 『百年の孤独』にトライしたが挫折した、という人は、話の全体を理解しようとするから失敗したと思う。全体など気にせず、小さなところに反応すればいい。読書感想文や作品要約(ついでに採点も)さようなら!だ。
そんな窮屈な気持ちではいないつもりでも、読みながら「作者はこういうことを言いたいのか?」と、つい答え合わせ的な思考を巡らせてしまうものだが、もう子供じゃない。大人なんだから、本を読みながら作者の意図などと離れていろんな連想をしてしまうのは当然というものだ。大人は子供より知識も経験も多いんだから、その分、連想は遠くまで広がってゆく。脈絡ない連想も多いだろうが、それを自己規制してたらつまらない。連想の赴くまま、あれやこれや思い出したりしながら読めばいい。
私は前から思っているんだが、
(1)いい本は、読者の記憶をフル稼働させてくれて、思いがけないことまで思い出される。
(2)いい本は、読むたびに発見する面白さがあって、作品世界が彩り豊かになる。
『〜を代わりに読む』は、この2条件を証明している。ーーそして、じつはもう一つ、
(3)この人、なんでこんなこと書くんだ?この人、バカなの?
と、つい思ってしまうところが、いい本にはある。「大作家」「名作」というラベルに萎縮せず、肩の力を抜いて読むとその感じが不意に訪れる。私が(3)を発見したのも『百年の孤独』だった。三十歳で再読しているときだった、
「この人、バカなのかもーー」
という感覚に不意に襲われ、それを境に面白さは倍化した。
二冊目『プルーストを読む生活』。
柿内正午さんが、全十巻の『失われた時を求めて』を読んでいた丸一年とちょっとの日々の日記や読書の記録などが書かれている。その10日目。
「今日も朝の通勤電車でプルーストを読んでいた。
今朝の「私」は散歩をする。歩いているうちにテンションが上がってきて「ちぇっ、ちぇっ、ちぇっ」と奇声を発しながら傘を振り回す。歩きながら、この田舎道でヤらせてくれるエロい農家の娘とばったり出会えたりしないかなあなどと妄想し、もちろん出会えず、トイレでオナニーをする。これらが文彩豊かに、回りくどく描写される。プルーストは馬鹿なのかもしれない。」
柿内正午さんもここで、さっきの(3)を発見している(誤解のないよう書き添えておくと、同じ日の日記で「性の話はプルーストは好きみたいだが僕は少し苦手だ」と書いている)。柿内さんは(1)についても142~3ページに書いてる。書き写したいところだが、自分が書いたこととダブるし、紙面の制約もあるので割愛。
『〜を代わりに読む』もそうだったが、この本と次の『読書の日記』は読んでいる本の書き写し(抜き書き)が多い。学校では要約はさせられたが書き写しはさせられなかった。同じく、感想文は書かせられたが連想文はなかった。
要約や感想文は型にはまっていて読書の楽しみから遠い。書き写しと連想こそが読書の楽しみで、AIに感想文は書けても連想文は書けない(たぶん)。
柿内さんは本を買いもするが借りもする。借金ならぬ「借本で首が回らない」(p.620)なんて書いてるくらいで、一度に上限の二十冊借りたりして節度がないが、この節度のなさは見習いたい。人は何ごとにつけても節度を持ってしまう。体でする行動も頭の中でする連想も、みんな、誰から言われたわけでもないのに、ほどほどのところで歯止めをかけてしまう。私のこの文章がどこまで説得力あるか、わからないが、歯止めは自分ひとりのものであるはずの空間を社会に譲り渡すことに通じる。読書は社会から身を守る砦だ。
節度のなさ、歯止めのなさの代表が『読書の日記』の阿久津隆さんだ。
私は女性誌だというのに男ばっかり三人を選んでしまったが、この三人は世間の「男性性」(昔の言葉で「マッチョ」)とはほど遠い。というか、この三人を知れば、世の中にある二分法が無意味とよくわかる。男女の二分法だけじゃない。無駄話がいつの間にか核心を射抜く。へなへなしてるのに心は折れない。
『読書の日記』はシリーズでこれは今のところ最新で六冊目(「皮算用/ストレッチ/屋上」という副題つき)。文庫サイズだが660頁で厚さは5cm(『プルーストを読む生活』も普通の本のサイズで750頁超)それで5月23日から9月10日まで110日分。1日平均して3600文字くらいか。すごい量だ。それを阿久津さんはfuzkueという本を読む店を経営しながら本も日々いっぱい読みながら書いた。
阿久津さんの文章からは、アスリートの躍動を見るみたいな元気をもらえる。みんなが、空気を読んで、そこそこに留めている時代に、天然の多動で自分の世界を切り開いている。手当たり次第に本を読む。本への根本的な信頼がある。凹む日もあるが、本を読むと立ち直ってる。
友田さんも柿内さんも、三者三様に、本を読むということが、社会に埋没せず、自分のための空間を確保することだということを証明してくれている。この三人の独自性に、ひとりでも多くの人が触れてくれたら、きっと明日は明るい。