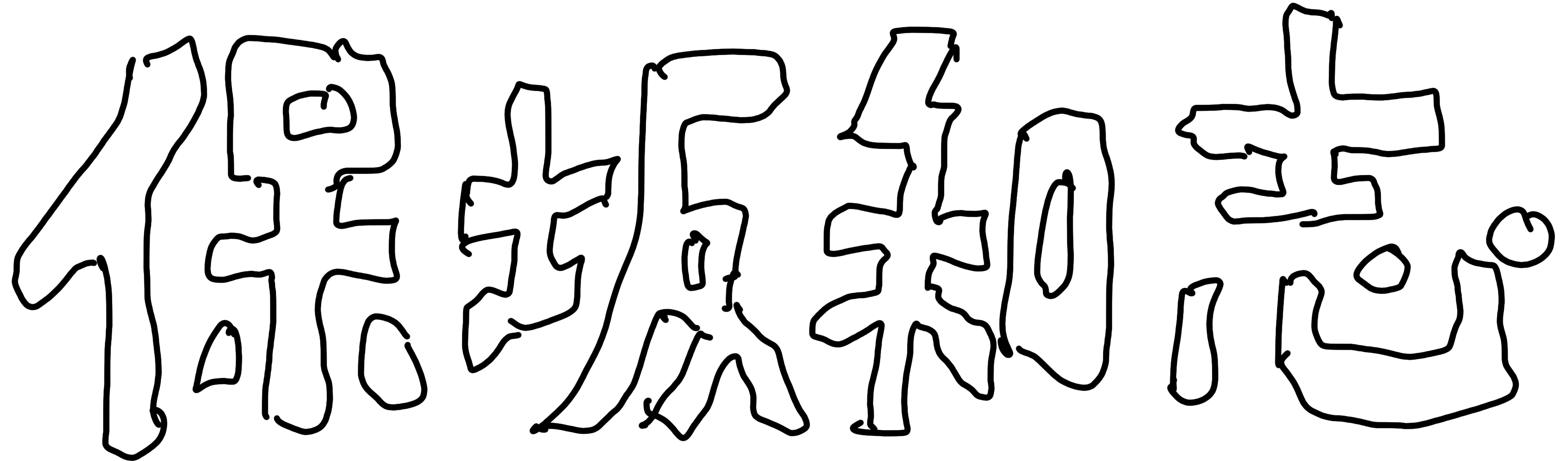Xとなる以前の初期Twitterは、社会に流通しやすい形(言葉・文章)になる以前の小さな思いをつぶやく場だった
水面に生まれた小さな波紋のTweetをたまたま見つけた人が、
「たぶん私もあなたと同じことを感じてました」
と控えめに応答する
つぶやきは〈個〉で留まり〈多数〉にならない。
多数になると言葉は雑になり、つぶやいた最初の気持ちから離れてしまう
そこから《物語神話歴史》は始まり、最初の繊細さはない
〈多数〉にならず、〈個〉や〈少数〉に留まるためには、自覚的な強い意志がいるのです
…………………………………………
私(保坂和志)の周辺では、例外的に、カフカとベケットが知られていて、それを読んでる人が普通にいます。
しかしこれは世間的には、例外中の例外で、皆さんが社会で出会う人で、ベケットを読んでる人なんか、きっといないでしょう。
最近の芥川賞小説を読んだ人はいてもベケットを読んでる人はいない。
これが本当の少数者、社会的な意味を超えて、存在論的な意味で少数者です。
人から「分かられたい」と思って、自分の意志を曲げて書いたり作ったりするより、ベケットやカフカを読める自分を確認し、祝福するところから出発する
そこはもう数の論理とは相容れないけど、全く独りというわけではないのが、ここに来れば感じられるはず。
全く独りじゃないという実感は大切で、
自分の考えてることは曲げなくても誰かに理解されると思える→→今回はそういうことでもあるんだと思います。