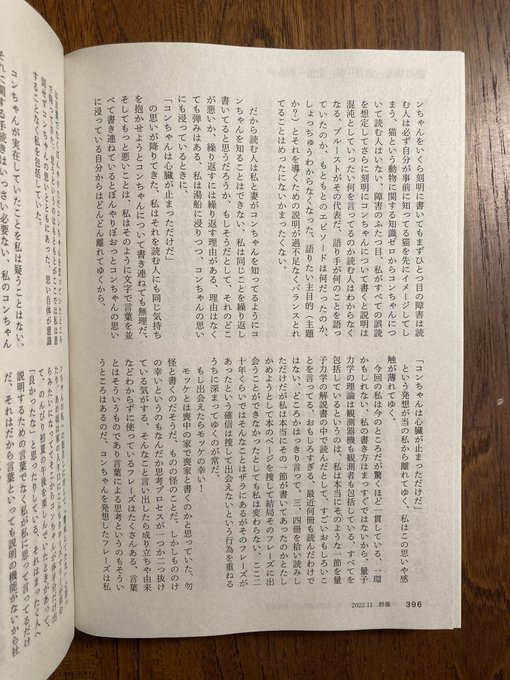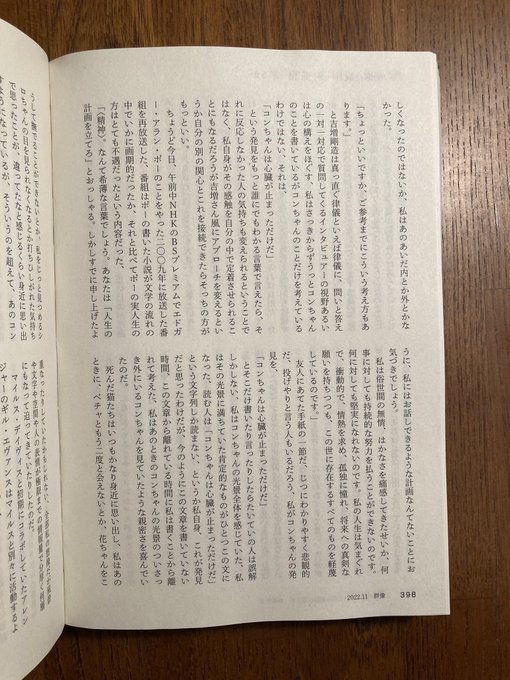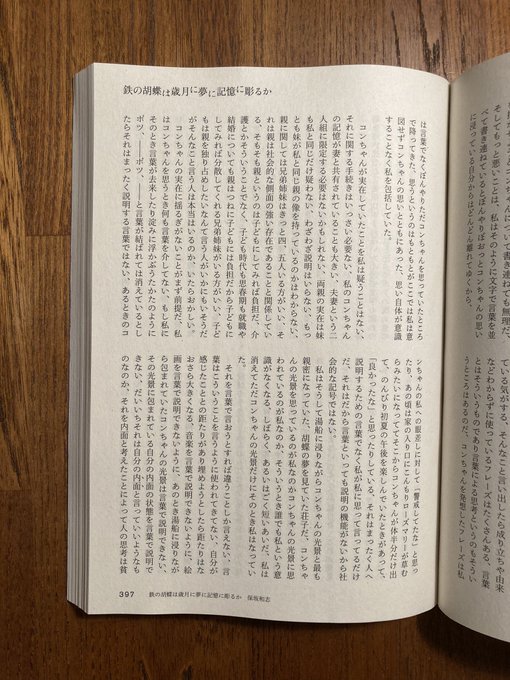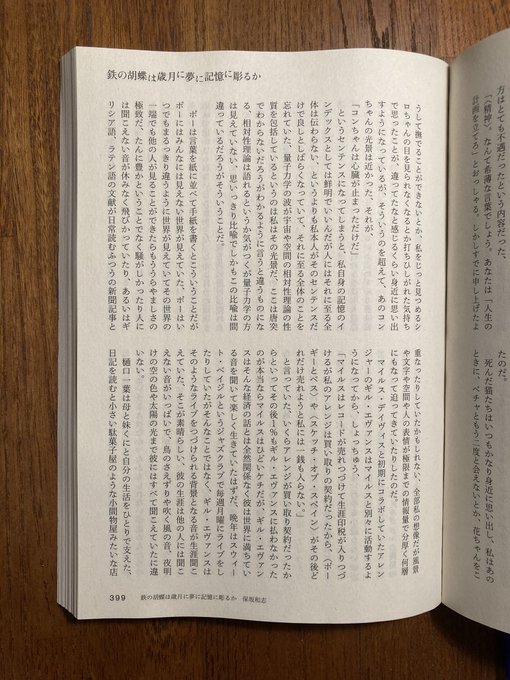人は考えているとき、考えの波間に漂っている。明確な焦点を持つ考えをしているときはある程度主体性があるが、私がここで、外にいた猫のコンちゃんを思い出したりしている時、私は「思い出す」のでなく、ただ「思い出ている」。
思い出のダダ漏れ状態だ。 ダダ漏れる思い出や記憶の実在を、ダダ漏れている最中、本人は疑わない。 しかしそれを言葉にしようとすると、言葉はいちいち記憶を点検するかのようになる。 いま目の前に風景が広がっているとする。風景は何の問題もなく、ただ目の前にある。
私は風景があるとかないとか疑わない。なのに、風景を言葉にしようとすると面倒くさいことになる。目を閉じて、わずか数秒前に見えていた風景の細部を列挙するのもできない。 記憶も目の前の風景も同じこと。 記憶を語る時、言葉は人をこの罠にハメる。